大地の記憶と自分の記憶を巡る旅。地球を「はぎ取る」展 体験レポート

山を歩いていると山肌が露出している光景をよく見かけます。その時はあまり気にせず山を歩きますが、そういう景色を何度か見ているうちに「地層」というものに惹かれていく自分がいました。
TwitterのTLにたまたま流れてきた「地球をはぎ取る」というキーワードに反応し、これは絶対に見に行きたいと決意したのが今回ご紹介する『地球を「はぎ取る」』展です。
今自分が立っているこの大地も長い時間をかけて作ってきた地球が紡いだ物語。その物語の中から誕生した人類もまた現在の僕たちをDNAで繋いできたことを考えると、壮大すぎて胸が高まります。
地球を母体にして全ての生命に繋がりを感じてしまう、そんな妄想をしながら会場へ向かいます。
※この展示は神奈川県立「生命の星・地球館」にて2017年7月15日から11月5日まで行われました(イベントは既に終了しています)
※撮影の許可をいただいております
【特別展】地球を「はぎ取る」~地層が伝える大地の記憶~展とは

『地球を「はぎ取る」』展が開催された場所は、神奈川県立「生命の星・地球館」。小田原市にある地球を学ぶための立派な博物館です。恐竜や古代の化石などの展示物に触れながら地球の歴史を知るこができ、自然や生命のことを考えるきかっけになる様々な企画が行われています。
小田原市と聞くと北条氏が統治していた「小田原城」を思い浮かべますが、博物館が建てられている小田原市入生田には隠れた名所「長興山紹太寺のしだれ桜」があります。桜の時期に博物館としだれ桜を見に来るのもよいですね。
今回行われた展示は露出された地層の一部を最新技術を駆使して、そのまま標本にしたものが展示されています。地球の記憶を巡る旅に出かけるようなワクワクした気持ちで、念願の『地球を「はぎ取る」』展に行ってきま〜す。
地層は時間によって形作られ、場所や出来事によって特徴づけられる

地層とは層状にかたまった粒子(岩体)のこと。その時代に起きた事象によっていくつもの層が積み重なってできています。世界的にわかりやすい地層はアメリカにあるグランドキャニオン。その壮大な景色は一度は見てみたいですね。日本では磁場逆転の記録が残る「チバニアン」が話題になってます。
場所によって地層の作られ方も変わります。陸地では雨や風によって流されてきた岩や土が川に辿り着き、川の流れによって岩は砕かれ、砂は泥になりやがで細かい粒子となり時間をかけて地層が形成されます。一つの層には岩石、石ころ、砂、泥などいくつもの粒子が混ざっているのです。
海底では噴火による火山灰やサンゴ礁、貝、生物などの死骸が積み重なった地層が作られていきます。山の中には火山灰を多く含んだ地質がありますが、それは積み重ねられた地層が地上に出てきた証です。その出てきた地層を僕たちが登っているというのは、面白い構造ですね。
「出来事」ではその時代に起こった事象が関係します。主に地震や火山による影響によって蓄積された地層が展示されていました。過去3回あったという富士山の噴火、今でも活動している箱根山の噴火の歴史も地層から読み取ることができます。
「場所」「時間」「出来事」によって作られた様々な展示を写真でいくつかご紹介します。

約2億4000年前の深い深い海底にあった地層。黒い地層から赤い地層へと変わっている特徴的な地層ですね。酸素不足だった時期から徐々に回復していった様子がわかる環境の大変動を記録しています。
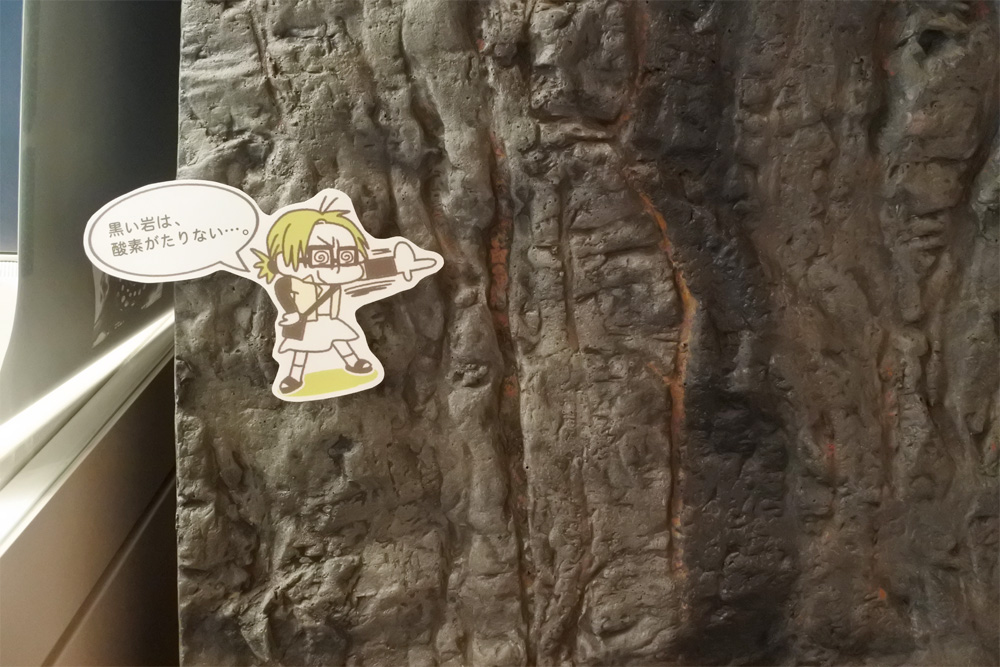

展示には所々イラスト付きのコメントが書かれていました。わかりやすくポイントが書かれている嬉しい配慮。

100万年前ぐらいの海底斜面の地層。地層の中に含まれていた水が一気に上へ抜けたときの記録が残っています。一つ一つの層も一緒に上へ流れた様子がわかりますね。自然に勝るアートはないとよく聞きますが、まさにその通りでとても綺麗な地層です。

約3万年前に起きた地震により、大地が動いた形跡が見られる地層。左と右で全く違う地層が隣り合わせになっているのが見た目でわかりますね。1,000年あたり1m動いたという…地震による影響は計り知れない。

江戸時代の時に噴火した富士山や箱根火山の痕跡が見られる地層。箱根山は2015年にも噴火している今でも活動している火山。箱根山に限らず、火山として認定されている山に行く時は活動状況を確認していますが、いつ起きるのか明確ではないので判断が難しいですね。
今でも各地で火山活動が行われていますが、その歴史が現在進行形で大地に刻み込まれていると思うと、自分たちも歴史の中の一部なんだなと想像が膨らむ。

なんと!約2万9千年前に南九州の姶良カルデラで起きた噴火から飛んできた火山灰も地層の一部として残っています。この地層は神奈川県厚木市でとれたもの。南九州から神奈川までの距離を考えると、とてつもない巨大噴火が起きたことがわかります。

展示の中でも一番大きかった地層。地震によって地盤が液状化し、液体のように流れている痕跡がくっきりと記録されています。
このように地層は「時間」と「場所」と「出来事」によって形作られていくのがわかりました。
一つ一つはただの岩石や火山灰でしかありませんが、地層全体で見てみると、しっかりとその時代の記録を残しているのです。なんだか僕たち人間の人生も似たようなものだと考えられますね。場所による違いは生まれた国や都道府県、どういう家庭環境かに当てはめられ、その場所でどのように過ごしたかによって生き方は変わってきます。
その他にも言語の違い、男女の違い、肌の違い、思想や文化の違い、お金持ちか、貧困か、何人家族か…。など色々要素は出てきますね。生まれた場所によってすでに培われた層ができているとすると、そこからどういう体験をして自分の層を積み重ねていくかが「出来事」になります。
少し大げさかもしれませんが、例え不遇な人生経験をすることがあったとしても、それよりも大きな層を積み重ねることで、逆に色鮮やかな地層(人生)を作れるのではないでしょうか。その色が人生の個性、深みなのかなと展示を見ながら考えていました。
地球をはぎ取り記録を読むことは、人生の記録を読むことにも似ている
かつて地層を記録するには写真やスケッチなどの方法しかありませんでした。技術が発達した現在では保存科学や造形学を組み合わせた様々な方法で地層を記録することができるようになったのです。
今回の地層の展示では下の3つの方法をもちいて標本を作っているようです。
・地層の表面の粒子をはぎ取る
・表面の形状の型を取る
・地層の固まりを切る取る
地層の形や固さ、質によって使う技法は変わりますが、今回のように地層の標本を見るのは始めてなのでその技術には驚かされます。

展示では地層の表面の粒子をはぎ取る様子の動画が上映されていました。地層の表面に接着剤を塗り、バリバリとはいでいく様子は、まさに「地球をはぎ取る」行為そのもの。
技術の発達のおかげでハンマーで地層の一部を砕いて一つ一つを研究していたころに比べると、より広い範囲で地層を保存することが可能になったとされています。これまで何千万年という時間をかけて形成された地層を標本として保存することはとても貴重なことで後世に残す重要な遺産ですね。
もし、自分の人生を標本にするとどうなるのか少し考えてしまいました。生まれてから現在に至るまで何をしてきたのか…と。
それほど劇的な人生を歩んできたわけではないので恥ずかしいのですが、変わったなあと思える時期は今のところ大きく6つ。
(1)中学一年生の時の転校
(2)高校デビューを果たす
(3)就職してデザイナーになる
(4)紙媒体からWEB業界に切り替える(デザイナー卒業)
(5)クライアントワークから自社サービス運営へ切り替える
(6)山との出会い
地層のように違いをつけるとすると上記の時期が、違いや色を変えるきっかけとなっていると自分で思っています。
(1)はそのままですが、中学一年生の時に転校しました。思春期の時の転校はなかなか心に響きます。この後、中学二年、三年と学年ごとに転校したので、どうしても内にこもってしまいおとなしい中学時代を送ります。
(2)は、中学のころの反動なのか、急に世界が開けたように恥ずかしながら高校デビューを果たします。笑。
細かいことに悩むことをやめて色々吹っ切れた時期でもあります。
(3)~(5)は仕事のことですね。デザインから入り、転職をしつつ、サービス作りの道を進んでいきます。やることや視点が変わった時期を指していますが、大きな目線でみると同じようなものなので一つに絞っても良いかもです。
そして(6)は山との出会い。なんとなく始めた登山をここまで好きになれたのは人生に大きなインパクトを与えた出来事です。それまでは趣味もなく、仕事に時間を費やしていただけでしたが、山は今後の暮らしを考えるきっかけになったとても重要なファクターになりました。
この山コミュができたのも今までの経験があってこそ。今まで歩んできたこと全てが何処かにつながっていると思うと、感慨深いものになりますね。

最後に僕たちの祖先でもある縄文時代の暮らしの証がわかる地層をご紹介します。

貝殻以外にも埋葬された人や犬の骨まで発見されたことから、貝殻を捨てる場所ではなく、埋葬するための特別な場所だったのではと予測できます。縄文時代の人々はどのような人生を送ってきたのか…。そんなことまで考えさせられる展示でした。
僕たちが生きている現在進行形の今も、いずれ記録として残り、未来の人へと繋がっていく。地球の物語の一つとして語り継がれていくと思うと、なんだか不思議な気持ちになります。
まとめ
「大地の記憶と自分の記憶を巡る旅」として地層の作られ方が、人の人生の作られ方にも似ているなあと思い、このようなテーマにしました。地質の知識がもっと自分にあったら、また別の視点があっただろうと思います。簡単に習得できるものでもなさそうですが、地質学は山の成り立ちを知る上で、とても大切な知識ということがわかりました。
例えば関東にある丹沢系と秩父系の山では同じ低山でもどことなく歩く感触が違います。その違いを知るためには山がどうやって作られたかを紐解いていくことでわかるのかもしれません。より山を楽しむためにも地質学を少しずつ蓄えていきたいものです。
自分や誰かの人生と向き合うように、山の人生「山生」と向き合うことは、自分が目指している登山の一つの姿かもしれないことに気付かされました。本当に山は奥深く、どことなく知的なものと改めて実感できる展示会でした。
今回体験レポートしたところ
「生命の星・地球館」までのアクセスは新宿から小田急線で「小田原駅」まで約1時間30分かけて行きます。一度降りて箱根登山電車に乗り替え、「小田原駅」から約10分の「入生田駅」で降ります。「入生田駅」からは徒歩10分ぐらいで「生命の星・地球館」到着します。看板があるので迷うことはありません。
小田原城の観光をしつつ、「箱根湯本駅」も近いため温泉に立ち寄ることもできますよ。

- 【住所】
- 〒250-0031 神奈川県小田原市入生田499
- 【開館時間】
- 9:00~16:30(最終入館 16:00)
- 【休館日】
- ・月曜日(祝日・振替休日にあたる場合は翌平日)
・館内整備日(8月を除く、原則として毎月第2火曜日、12月・1月・2月の火曜日)
・年末年始
・燻蒸期間
・国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日または国民の祝日等にあたるときを除く)
※このほかに臨時開館日、休館日があります。詳しくは直接ご確認ください。 - 【TEL】
- 0465-21-1515
- 【設備】
- 特別展示、常設展示、SEISAミュージアムシアター、ミュージアムライブラリ、レストラン・喫茶、ミュージアムショップなど
※地球を「はぎ取る」展は期間限定の特別展示です。年間を通じて様々な展示を開催しています。詳しくは直接ご確認ください。

HIKES編集長。ハイク歴6年。低山・里山などの山道を歩くのが好きです。里山暮らしに憧れ東京から長野県安曇野市へ移住。森の中のログハウスで理想のライフスタイルを目指してます。里山・山歩き・キャンプ・山城・ガーデニングなどをテーマに発信しています。
関連記事
この記事に関連するキーワード
新着マガジン
-

【那須岳(茶臼岳・朝日岳)】火山のダイナミックな光景と紅葉をロープウェイを利用して楽しむ日帰り登山
那須岳(なすだけ)は栃木県北部に位置する那須連山、特に「茶臼岳(ちゃうすだけ)」「朝日岳(あさひだけ…
-

【岩木山】青森県の最高峰を九合目からお手軽に登頂
津軽平野の南西にそびえる岩木山は、青森県の最高峰で日本百名山に選定されています。その美しい円錐型の山…
-

【男体山】中禅寺湖を振り返りながら奥日光の霊山を登る日帰り登山
男体山は中禅寺湖の北側にそびえる、美しい円錐形の山です。古来、日光二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ、…
-

【木曽駒ヶ岳】初心者でもロープウェイで中央アルプス最高峰へ!千畳敷カールの絶景が待つ日帰り登山
中央アルプス最高峰の木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)は標高3000mに迫る標高がありながら、ロープウェイ…
-

【大台ヶ原】豊かな自然と見どころ満載の東大台ハイキングコースを歩く
奈良県と三重県の県境に位置する「大台ヶ原(おおだいがはら)」は、日本百名山をはじめ、日本百景、日本の…
-

【奥多摩・御前山】奥多摩湖から始まる急登の連続!達成感を味わえる日帰り登山
大岳山(おおだけさん、おおたけさん)、三頭山(みとうさん)とともに奥多摩三山に数えられる「御前山(ご…
-

【塔ノ岳・登山】首都圏近郊の好展望の山!丹沢を代表する人気コース表尾根を歩く
表丹沢の「塔ノ岳(とうのだけ)」は、展望の良さと都心からのアクセスのしやすさで人気の山です。標高は1…
-

【檜洞丸】西丹沢の秘境を巡る日帰り登山!アクセスと難易度、絶景ポイントを紹介
檜洞丸(ひのきぼらまる)は西丹沢の山深さが感じられる静かな山で、「西丹沢の盟主」とも呼ばれています。…
-

【袈裟丸山】花見登山を満喫!山肌をピンクに彩るアカヤシオの名山を歩く
栃木・群馬県境の足尾山地に属する袈裟丸山(けさまるやま)は、アカヤシオの名所として名高い山で、シーズ…
-

【大楠山・登山】三浦半島を横断!海と山の360°パノラマが楽しめる低山ハイキング
神奈川県三浦半島の最高峰、大楠山(おおぐすやま)。海に囲まれた半島に位置するため、東京湾、房総半島、…
-

【群馬・根本山】自然のアスレチック!低山ながらスリルと登りごたえのある古道歩き
栃木・群馬両県の百名山に選定されている「根本山」は、古くから信仰の山として親しまれています。根本山へ…
-

【丹沢・不動尻】一面黄色の世界!早春のハイキングで「ミツマタ」を見に行こう!
春が来て登山・ハイキングに最適なシーズンとなりました。春ハイキングの楽しみのひとつに、山で出合うお花…
-

トレイルランと登山の違いを解説!自分に合った山のスタイルを見つけよう
トレイルランと登山は、山を「走る」のか「歩く」のかという違いだけで、似たようなものだと思いがちですが…
-

【積雪期・谷川岳】雪山初心者におすすめ!日帰りで360度白銀の世界へ
「トマの耳」「オキの耳」の双耳峰(そうじほう)からなる「谷川岳(たにがわだけ)」は、日本百名山のひと…
-

【伊豆ヶ岳】奥武蔵屈指の人気コースを歩く日帰り縦走登山
気軽にハイキングが楽しめる低山の多い奥武蔵エリア。その中でも一番人気といわれるのが伊豆ヶ岳(いずがた…
-

【皆野アルプス】身近な里山のアルプスを縦走する日帰り登山(破風山・前原山・大前山・天狗山)
皆野アルプスは破風山をはじめとしたいくつかのピークをつなぐ低山縦走コースです。最高峰の大前山でも65…
-

【三国山・鉄砲木ノ頭】富士山の絶景を満喫するハイキングコース
丹沢山地の西端、山中湖の近くに位置する「三国山(みくにやま)」は、神奈川県、山梨県、静岡県の3県にま…
-

【丹沢・大山】都心からアクセス抜群!大山阿夫利神社と紅葉スポットを散策する日帰り登山
関東屈指の人気の山域、丹沢の東側に位置する大山は、ピラミダルな美しい山容が特徴の山です。古くから山岳…
-

【鳥取・大山】初心者でも安心!自然と歴史満喫の夏山登山道、行者コースを歩く
鳥取県西部に位置する「大山(だいせん)」は、西日本最大級のブナ林や国の特別天然記念物ダイセンキャラボ…
-

【棒ノ折山・登山】「鎌倉殿の13人」畠山重忠ゆかりの山!渓谷を沢登り気分で楽しむ日帰り登山
奥武蔵エリアにある「棒ノ折山(ぼうのおれやま)」は、渓流沿いのコースで沢歩き気分が楽しめる山です。ゴ…

